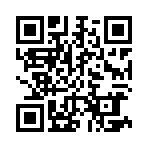2020年02月17日
NHKスペシャルを見て(前編)
土曜日にNHKスペシャルの放送がありました。
見ていただいた方、ありがとうございます!
見られていない方も再放送がございますので
コチラをチェックいただけたらと思います。
私が見た率直な感想としては
車中生活者それぞれの思いや事情にフォーカスするだけでなく
彼ら(すべての方たちではないですが)が支援を受ける事を決意した
「その後」の様子をもっと紹介してほしかったなと思うところです。
我々が行っている一時生活支援事業(富士POPOLOハウス)は
まさにこのような方たちが現状を憂い
「何とかしたい」と思ったときに
使えるような事業です。
富士POPOLOハウスでは
①衣食住
②今後についての相談
③就労支援、行政手続き支援
といったサービスを無料で受けることができ
「住所がない!」といった方も、就労自立を目指すことができます。
もちろん、人それぞれ事情は様々ですので
すぐに就労自立をするのが難しい方もいらっしゃいます。
そういった方には生活保護受給を含め、いくつかの選択肢の中
可能な限り本人の意思に沿うような支援をしていきます。
ざっくり言ってしまうと
「家がない人に施設に入ってもらい、その間に収入と住居を見つけることを目指す」
ところなのですが、この事業には課題もいくつかあります。
(1)実施自治体の少なさ
一時生活支援事業は生活困窮者自立支援法に基づく事業です。
つまり、国がルールを定め地方自治体が主体となって実施している事業なのですが
「任意事業」とされており
その実施は地方自治体の判断に委ねられております。
平成30年度の統計によると
一時生活支援事業を実施している自治体は
全国の31%程度にとどまっており
まだまだ十分とは言えません。
静岡県においても
我々POPOLOと協定を結んでいるのが12市
独自で行っているのが2市、県が統括して行っているのが町部と、
すべての自治体で、というわけにはいかないのが現状です(平成31年度)。
(2)スタートラインに立つためのハードル
この困窮者の制度はまだまだマイナーです。
なので、そもそもこの仕組みを知らないという方が多いです。
また、この制度も「本人意思に基づいて行う」のが原則となっており
番組ででてきたように「自分が好きでやっている」といったケースにおいては
利用に繋がるスタートラインに立つまで、信頼関係を結んでいくなど
長い時間がかかることが考えられます。
(3)支援に繋がった後
支援に繋がってからも、本人の目標を達成するために
我々だけの力ではどうにもならないことが多々あります。
ですので、行政をはじめとした関係機関と、いかに連携していくか。
また、一時生活支援事業を利用したとしても、その人が帰る場所はその「地域」になります。
「地域の方々の理解を得る」ということも、まだまだ不十分に感じます。
このように様々な課題がありますが
まずは支援を求める対象者と向き合い
一つずつ問題を本人を含めた「皆」で解決していくこと。
そして、ときには周りを巻き込んでいくような
NPO「らしい」活動をしていくことが重要だと思っております。
(長くなるので)後編に続きます。

見ていただいた方、ありがとうございます!
見られていない方も再放送がございますので
コチラをチェックいただけたらと思います。
私が見た率直な感想としては
車中生活者それぞれの思いや事情にフォーカスするだけでなく
彼ら(すべての方たちではないですが)が支援を受ける事を決意した
「その後」の様子をもっと紹介してほしかったなと思うところです。
我々が行っている一時生活支援事業(富士POPOLOハウス)は
まさにこのような方たちが現状を憂い
「何とかしたい」と思ったときに
使えるような事業です。
富士POPOLOハウスでは
①衣食住
②今後についての相談
③就労支援、行政手続き支援
といったサービスを無料で受けることができ
「住所がない!」といった方も、就労自立を目指すことができます。
もちろん、人それぞれ事情は様々ですので
すぐに就労自立をするのが難しい方もいらっしゃいます。
そういった方には生活保護受給を含め、いくつかの選択肢の中
可能な限り本人の意思に沿うような支援をしていきます。
ざっくり言ってしまうと
「家がない人に施設に入ってもらい、その間に収入と住居を見つけることを目指す」
ところなのですが、この事業には課題もいくつかあります。
(1)実施自治体の少なさ
一時生活支援事業は生活困窮者自立支援法に基づく事業です。
つまり、国がルールを定め地方自治体が主体となって実施している事業なのですが
「任意事業」とされており
その実施は地方自治体の判断に委ねられております。
平成30年度の統計によると
一時生活支援事業を実施している自治体は
全国の31%程度にとどまっており
まだまだ十分とは言えません。
静岡県においても
我々POPOLOと協定を結んでいるのが12市
独自で行っているのが2市、県が統括して行っているのが町部と、
すべての自治体で、というわけにはいかないのが現状です(平成31年度)。
(2)スタートラインに立つためのハードル
この困窮者の制度はまだまだマイナーです。
なので、そもそもこの仕組みを知らないという方が多いです。
また、この制度も「本人意思に基づいて行う」のが原則となっており
番組ででてきたように「自分が好きでやっている」といったケースにおいては
利用に繋がるスタートラインに立つまで、信頼関係を結んでいくなど
長い時間がかかることが考えられます。
(3)支援に繋がった後
支援に繋がってからも、本人の目標を達成するために
我々だけの力ではどうにもならないことが多々あります。
ですので、行政をはじめとした関係機関と、いかに連携していくか。
また、一時生活支援事業を利用したとしても、その人が帰る場所はその「地域」になります。
「地域の方々の理解を得る」ということも、まだまだ不十分に感じます。
このように様々な課題がありますが
まずは支援を求める対象者と向き合い
一つずつ問題を本人を含めた「皆」で解決していくこと。
そして、ときには周りを巻き込んでいくような
NPO「らしい」活動をしていくことが重要だと思っております。
(長くなるので)後編に続きます。
コンサートスタッフを行ってきました!
課題解決プロジェクトについてご協力のお願い
令和6年能登半島地震での支援活動について
赤い羽根共同募金助成「中間的就労」にて
課題解決プロジェクトへのご協力のお願い
新年のご挨拶
課題解決プロジェクトについてご協力のお願い
令和6年能登半島地震での支援活動について
赤い羽根共同募金助成「中間的就労」にて
課題解決プロジェクトへのご協力のお願い
新年のご挨拶