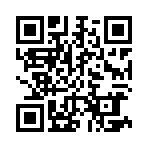2011年05月07日
東日本大震災 ボランティア報告 その①
はじめまして。今回、被災地に届けに行った一人の駒井といいます。
今回のプロジェクトに参加させていただき、5/2の夜から、5/5まで、
福島県新地町、宮城県栗原市、気仙沼市に行かせていただきました。
先に、このプロジェクトを支え、応援してくださった方々、
支援物資を届けてくださった皆様。
ほんとに、ありがとうございました。静岡からの気持ち届けてきました。
まずは、5/1~5/2の仕分け作業から。
たくさんの食器、急須、お湯呑、お茶が集まりました。
皆様が届けてくださったものを、種類ごとに分けるのが、仕分け。
どれが、どのくらい集まっているのかを知ることと、この先の栗原市に届けた後の
さらなる仕分けで、少しでも楽になるように。
なかなか時間がかかる作業でした。形や大きさが様々。
何かを集めるというのは難しさも大変さを感じました。
そして、積み込みをし、いよいよ出発。
車2台、2tトラック1台、総勢16名
自分は2tトラックの運転手の1人。
1日目(5/3)、トラックだけ、福島県新地町経由の指示を受け、
途中のSAを最後に仲間たちと別行動に。
途中の東北道にて、朝日による虹を見ながら福島入り。
向かうは、福島県新地町。
東北道から南下していき、海の方へ。さすが福島県。田園がきれい。
そろそろ田植えの季節。農家のみなさんは、田に水をはり始めていた。
そんな景色を横目に、無事予定時刻前に新地町に到着。
POPOLOでたくさんの支援物資が集まり、他にも届けたいため
新地町に届けにきたトラック部隊の2人の目に入ってきたのは、
たった1本の道路を境に海側は津波の被害で、一切何もなくなってしまったところもあった。
反対側は、河川沿いの被害はあるものの、大きな被害はない。
この境にまず大きく唖然としてしまった。
なにかしたいと来た自分の無力さを目の当たりし、
何かを思うことと、ほんとにできることには大きな差が生まれていること。
そんな気持ちを抱きつつ、新地町のボランティアセンター(VC)へ。
担当の方に挨拶をし、指示を受ける。
VCではたくさんのボランティアの方々が朝早くから集まっていました。
自分たちの荷物降ろしにも5人のボランティアの方が手伝ってくださいました。
一人の方が降ろす場所を聞きに行き、帰ってくると他のメンバーに指示。
黙々と作業していただき、動きがキビキビしていた。
運び出しは、あっという間に終わる。
あたりを見渡すと、他もリーダーが他のメンバーを引き連れ指示を出していた。
この運営形態はすごく効率いいなぁと感じた。
近くにいた、ボランティアの方と少し会話をしました。
ボ:「どっからきたの?」
駒:「静岡から来ました。」
ボ:「そうかぁ。これから帰るの?」
駒:「他の仲間が栗原市に向かっていて、荷物を持って、これから合流です。」
ボ:「まだ、走るんだね。気をつけていっておいで」
駒:「はい。ありがとうございます。」
ほんの少しの会話。どこの方もわからないけど。
帰りトラックをバックさせてたら、会話した方と周りの人たちが
「まだいいよ!もっと下がってもいい!オーライ!!オーライ!!」
温かい。自分たちと同じ気持ちを抱き、きっとここにいるんだ。
たくさんの人が早い復興を祈っている。
みなさんに、「ありがとうございます!後を、お願いします!!」と
伝え、新地町を後にした。
いろいろ話もしたかったし、VCの様子も見たかったですが、
VCはたいへん忙しい様子なためと、自分たちも次の目的地、みんなとの
合流地の栗原市を目指して出発。
渋滞にあいながら、みんなのいる栗原市へ。
仕分けの作業が進んでおり、静岡からの物資を運び入れる。
あずまーれさん達と仕分け作業し、一日目は終了。
二日目。朝、薄暗い5時に栗原市から気仙沼市に向け出発。
気仙沼市に入るとはじめは地震の被害が見られた。しかし、やはり海の方は。
ネットやテレビで見た風景がリアルに目の前に広がる。
そして、人一人では何もできない無力さを感じた。
自然の力はそれほどまでに大きかった。
気仙沼市災害ボランティアセンター本吉支所に到着。
VCのお手伝いで、看板作りや物の移動なども手伝いながら、
被災地の方に持ってきたお茶を振る舞うこともできた。
自分は直接触れ合うことはなかったが、喜んでもらえた。
少しでも、ホッとしてもらえたのなら、良かったと思う。
そして、渋滞を避けるため、夜のうちに東北道を抜け、静岡に無事到着。
長いようで短かった3日間。何を思い、何を感じたかが大きな意味をなすが、
これから起こるかもしれない東海地震のための大きな勉強と経験になった。
今回のプロジェクトに参加させていただき、5/2の夜から、5/5まで、
福島県新地町、宮城県栗原市、気仙沼市に行かせていただきました。
先に、このプロジェクトを支え、応援してくださった方々、
支援物資を届けてくださった皆様。
ほんとに、ありがとうございました。静岡からの気持ち届けてきました。
まずは、5/1~5/2の仕分け作業から。
たくさんの食器、急須、お湯呑、お茶が集まりました。
皆様が届けてくださったものを、種類ごとに分けるのが、仕分け。
どれが、どのくらい集まっているのかを知ることと、この先の栗原市に届けた後の
さらなる仕分けで、少しでも楽になるように。
なかなか時間がかかる作業でした。形や大きさが様々。
何かを集めるというのは難しさも大変さを感じました。
そして、積み込みをし、いよいよ出発。
車2台、2tトラック1台、総勢16名
自分は2tトラックの運転手の1人。
1日目(5/3)、トラックだけ、福島県新地町経由の指示を受け、
途中のSAを最後に仲間たちと別行動に。
途中の東北道にて、朝日による虹を見ながら福島入り。
向かうは、福島県新地町。
東北道から南下していき、海の方へ。さすが福島県。田園がきれい。
そろそろ田植えの季節。農家のみなさんは、田に水をはり始めていた。
そんな景色を横目に、無事予定時刻前に新地町に到着。
POPOLOでたくさんの支援物資が集まり、他にも届けたいため
新地町に届けにきたトラック部隊の2人の目に入ってきたのは、
たった1本の道路を境に海側は津波の被害で、一切何もなくなってしまったところもあった。
反対側は、河川沿いの被害はあるものの、大きな被害はない。
この境にまず大きく唖然としてしまった。
なにかしたいと来た自分の無力さを目の当たりし、
何かを思うことと、ほんとにできることには大きな差が生まれていること。
そんな気持ちを抱きつつ、新地町のボランティアセンター(VC)へ。
担当の方に挨拶をし、指示を受ける。
VCではたくさんのボランティアの方々が朝早くから集まっていました。
自分たちの荷物降ろしにも5人のボランティアの方が手伝ってくださいました。
一人の方が降ろす場所を聞きに行き、帰ってくると他のメンバーに指示。
黙々と作業していただき、動きがキビキビしていた。
運び出しは、あっという間に終わる。
あたりを見渡すと、他もリーダーが他のメンバーを引き連れ指示を出していた。
この運営形態はすごく効率いいなぁと感じた。
近くにいた、ボランティアの方と少し会話をしました。
ボ:「どっからきたの?」
駒:「静岡から来ました。」
ボ:「そうかぁ。これから帰るの?」
駒:「他の仲間が栗原市に向かっていて、荷物を持って、これから合流です。」
ボ:「まだ、走るんだね。気をつけていっておいで」
駒:「はい。ありがとうございます。」
ほんの少しの会話。どこの方もわからないけど。
帰りトラックをバックさせてたら、会話した方と周りの人たちが
「まだいいよ!もっと下がってもいい!オーライ!!オーライ!!」
温かい。自分たちと同じ気持ちを抱き、きっとここにいるんだ。
たくさんの人が早い復興を祈っている。
みなさんに、「ありがとうございます!後を、お願いします!!」と
伝え、新地町を後にした。
いろいろ話もしたかったし、VCの様子も見たかったですが、
VCはたいへん忙しい様子なためと、自分たちも次の目的地、みんなとの
合流地の栗原市を目指して出発。
渋滞にあいながら、みんなのいる栗原市へ。
仕分けの作業が進んでおり、静岡からの物資を運び入れる。
あずまーれさん達と仕分け作業し、一日目は終了。
二日目。朝、薄暗い5時に栗原市から気仙沼市に向け出発。
気仙沼市に入るとはじめは地震の被害が見られた。しかし、やはり海の方は。
ネットやテレビで見た風景がリアルに目の前に広がる。
そして、人一人では何もできない無力さを感じた。
自然の力はそれほどまでに大きかった。
気仙沼市災害ボランティアセンター本吉支所に到着。
VCのお手伝いで、看板作りや物の移動なども手伝いながら、
被災地の方に持ってきたお茶を振る舞うこともできた。
自分は直接触れ合うことはなかったが、喜んでもらえた。
少しでも、ホッとしてもらえたのなら、良かったと思う。
そして、渋滞を避けるため、夜のうちに東北道を抜け、静岡に無事到着。
長いようで短かった3日間。何を思い、何を感じたかが大きな意味をなすが、
これから起こるかもしれない東海地震のための大きな勉強と経験になった。
再び被災地へ行きます。
東日本大震災支援企画に協力いただいている団体さま紹介
東日本大震災 ボランティア報告 その⑦
報告書の送付
東日本大震災 ボランティア報告 その⑥
東日本大震災 ボランティア報告 その⑤
東日本大震災支援企画に協力いただいている団体さま紹介
東日本大震災 ボランティア報告 その⑦
報告書の送付
東日本大震災 ボランティア報告 その⑥
東日本大震災 ボランティア報告 その⑤
Posted by NPO法人POPOLO at 11:34│Comments(0)
│東日本大震災